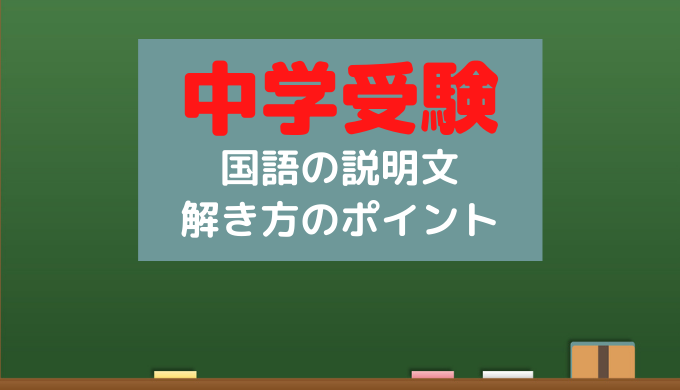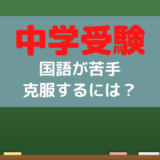中学受験の国語では、読解問題が必ず出題されます。
読解問題で出題される文章は説明文・物語文・随筆文があります。
文章のジャンルによって、それぞれ解き方のポイントが違ってきます。
今回は説明文の解き方のポイントについて詳しく見ていきましょう。
読解問題と読書との違い
読解問題と読書とでは違いがあります。
読解問題は文章を読んで答えを探す必要があります。
読書の場合、自分なりに楽しく読むだけで終わってしまうことが多くあります。
また、読書をするとき小学生の場合、物語を読むことが多いと思います。
中学入試で出題される説明文を読んでいる人は少ないでしょう。
したがって、読書をしているからといって、中学入試の説明文が出来るようになるとは限りません。
ただ、文章を読むスピードは上がるので、読書をするメリットはあります。
小学6年生になると、読書をする時間が限られてしまうので、中学受験のために読書をするのであれば、小学5年生までにしておきましょう。
読書を継続させるコツは、子供に好きな本を読ませることです。
無理やり読ませてもなかなか継続することはないので、興味がある本を好きなように読ませることが大切です。
説明文の構造を理解する
まず説明文とは、ある事柄について説明をする文章です。
説明文の構造を理解しておくことで、どこを探すと答えを見つけられるか分かるようになっていきます。
物語文よりも型が決まっているので、慣れてくると答えを見つけやすくなると思います。
- 話題
- 説明
- まとめ
説明文は上記のような流れで進むことが多いです。
話題の部分で「問いかけ」が出てくるケースが多くあります。
もちろん「問いかけ」に対する答えを筆者は知っています。
説明をした後で結果として、問いかけの答えが出てくることが多いので、意識してみましょう。
最後の部分では説明した結果、筆者の意見が書かれていることが多くあります。
筆者の意見についての問題が出題された場合、最後の段落を確認してみましょう。
傍線内の指示語に注意
読解問題では「傍線(1)について◯◯とあるが、これと同じことを言っている箇所を△△字以内で抜き出せ」といったような形式で出題されます。
ここで大切なことは、まず傍線内に指示語(「それ・これ・あの」など)が入っているか確認することです。
傍線の直前や同じ文の最初に指示語があるかも確認をするようにしましょう。
ここに指示語があった場合、答えやヒントが傍線より前にあるケースが多いです。
前を確認していくときの注意点として、いきなり段落の最初まで戻ったりするのでなく、1つ前の文から確認をするようにしましょう。
1つ前の文に答えやヒントがない場合は、もう1つ前の文に戻るようにして下さい。
そして答えもしくはヒントとなる部分を見つけてから、詳しく選択肢を見るようにすると、間違いが減ります。
抜き出しや記述の問題も同じで、答えもしくはヒントとなる部分を見つけたら、すぐ線を引きましょう。
そして字数の確認をし、必要な部分を答えとするようにしましょう。
- 傍線部に指示語が入っているか確認する
- 傍線部の直前、もしくは同じ文に指示語が入っているか確認する
- 指示語が入っている場合は、1つの前の文に戻る
逆接の接続後に注意
「A、しかしB」となっている場合、「しかし」の後(B)が重要です。
逆接の接続詞は説明文の中によく出てきます。
一度目に読んでいるときに、逆接の接続詞が出てきたら印をつけるようにすると良いでしょう。
逆接の接続詞には、「しかし・ところが・だが」などがあります。
また、説明文では「もちろんA、しかしB」といったように「もちろん」の後に一般論を持ってきて、その後で「しかし」などの逆接を使い、筆者の意見が述べられることがよくあります。
問題を作る人にとって、このような箇所はとても作りやすいためよく出題されます。
したがって、「もちろん」が出てきたら印をし、その後で出てくる「しかし」などの逆接の接続詞にも印をすることで正解を導き出すことが出来ます。
普段から「もちろん」が出たら逆接の接続詞が出てくると意識して読むことが出来るようになると、得点が取れるようになります。
- 逆接の接続詞の後が重要
- 「もちろん」が出てきたら逆接の接続詞が来るの待つ
例に惑わされないよう注意
ある事柄についての説明をしていく中で、内容が難しくなってくると「例」を出して説明をすることがあります。
「たとえば、〜」といった形で書かれている部分です。
「話題A→説明A→例B→まとめA」といったように、説明部分に例は出てきます。
ここで注意が必要なこととして、最初の話題と例は別物ということです。
そのため、例の部分が答えとなることは意外と少ないです。(問題によっては例の部分が答えとなることもあります)
説明の内容が難しい場合、例があると分かりやすくなるため、ついつい例の部分に答えを求めてしまう生徒がいます。
特に記述問題の答えを例の部分を使って書く生徒がいますが、例の部分は答えにならないことが多いので注意して下さい。
- 説明中に例が出ることがある
- 例の部分は答えにならないことが多い
最終段落の問題の答えの場所
最後の段落は、話題に対する筆者の意見が書かれていることが多いです。
そのため、筆者の意見を答えさせる問題は最後の段落に答えがあることが多くあります。
しかし、最後の段落中にある傍線の問題の答えが近くを探してもないケースがあります。
その場合、最初の段落に答えがあることが多いでしょう。
これも定番問題で、最初の段落と最後の段落が関係している説明文が多いため、問題を作るひとがよく使います。
無理やり傍線部の近くから答えを見つけようとすると、ひっかけにひっかかることになってしまいます。
算数と同じで問題の解き方を覚えておく必要あります。
また、逆のパターンもあります。
最初の段落にある傍線の答えが最後の段落にあるケースです。
ただ、このケースの問題は少ないので、まずは最後の段落の傍線の答えが最初の段落にあるということから覚えていきましょう。
- 筆者の意見は最後の段落にあることが多い
- 最後の段落にある傍線の答えは、最初の段落にあることも多い
まとめ
国語の読解問題にも解き方のポイントがあります。
解き方のポイントは説明文と物語文とでは違うので、文章のジャンルによってコツを掴むようにしましょう。
入試問題では塾のテキストのように、「説明文」「物語文」と書いていないので、出だしを読んでどちらなのかが分かるようにしましょう。
また、随筆文というジャンルもありますが、入試問題には「随筆文」とは書いてありません。
「次の文章を読んで後の問いに答えなさい」と書いてあるだけです。
随筆文は説明的随筆文・物語的随筆文に分かれますので、説明文と物語文と同じ解き方をしていきましょう。
個人的には型が決まっている説明文の方が読みやすいと思います。
説明文の型を覚え、指示語や接続語の問題の解き方を覚えていきましょう。
物語文の解き方のポイントにつきましては「【中学受験】国語の読解問題の解き方のポイント〜物語文編〜」をご覧下さい。
また、詩の解き方のポイントにつきましては「【中学受験】国語の読解問題のポイント〜詩編〜」をご覧下さい。