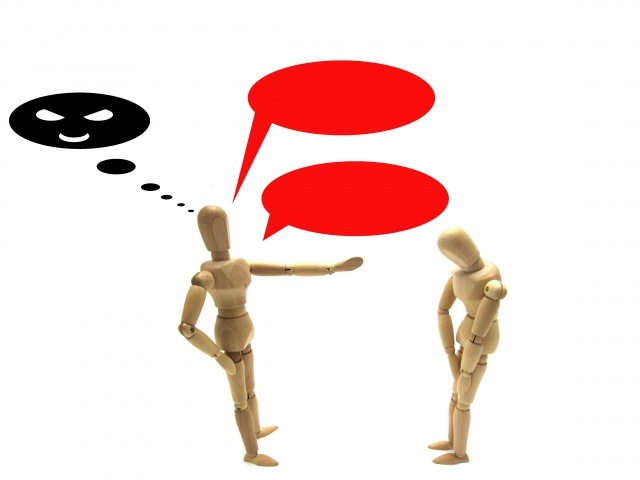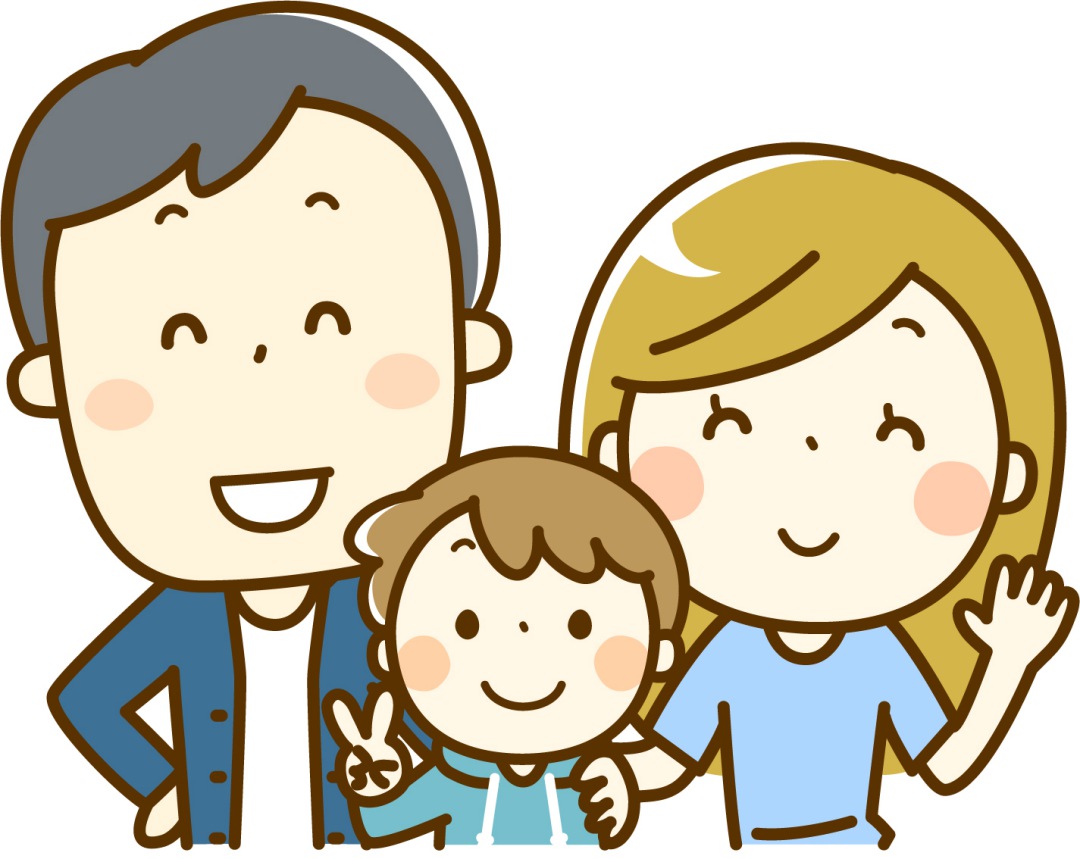公立高校を志望している人は内申点と入試での得点の2つを取る必要があります。普段の勉強を定期テストと入試の2つに結びつけることが出来たら効率的ではないでしょうか。
今回は社会の歴史の勉強を定期テストと入試に結びつける方法を考えてみたいと思います。特に歴史が苦手な人は苦手を意識をなくすことから始めましょう。
歴史の勉強に楽しさをプラス
歴史というと「暗記ばかりでつまらい」と思う人が多いのではないでしょうか。確かに暗記をしないと点数は取れません。しかし、嫌々覚えてもすぐに忘れてしまいます。そうすると「やっても出来ない」と思うようになってしまい、更に歴史が嫌いになってしまう可能性があります。
そこで、まずは「楽しい」と思えることから始めてみましょう。
直接的には定期テストや入試に関係ないことであっても歴史が好きになることを目的とします。そのため、興味のある時代や人物について調べるだけで構いません。調べるというか、ただ本や漫画を読むだけで構わないと思います。
もし、本や漫画を読んで興味がなかったら、他の時代や人物にすぐ変えてみましょう。どうしても興味が持てない場合は、最終手段として「ゲームの活用」もしてみてはどうでしょうか。
私が歴史に興味を持つきっけになったのは「信長の野望」というゲームでした。ゲームを通して、出て来る武将に名前を自然と覚え、育てた武将について興味が湧いて調べるようになりました。そこから派生して出来事についても調べるようになり、最終的には歴史が好きになったという経験があります。
まずは興味があるものから始めると長続きすると思います。
[amazonjs asin=”4041047021″ locale=”JP” title=”角川まんが学習シリーズ 日本の歴史 2017特典つき全15巻+別巻1冊セット”]- 漫画で各時代について確認する
- 小学生にも中学生にもおすすめです
[amazonjs asin=”4791623908″ locale=”JP” title=”超ビジュアル!日本の歴史大事典”]
- このシリーズは絵が綺麗です
- ビジュアルから歴史に興味を持てるかもしれません
ノートにまとめる
歴史に興味を持つことが出来たら、定期テストや公立高校の入試に向けた勉強を始めましょう。
いきなり問題を解くのではなく、自分専用の歴史ノートを作ることから始めます。
年号でまとめるのはNG
ノートにまとめるときに年号でまとめるのはおすすめ出来ません。重要な年号は覚えないいけませんが、年号だけを覚えようとしない方が良いでしょう。数字を無理やり覚えてもすぐに忘れてしまいますし、ただの暗記になってしまい苦痛を感じてしまうと思います。
[amazonjs asin=”4046008601″ locale=”JP” title=”高校入試 ここで差がつく! ゴロ合わせで覚える歴史80″]- 語呂合わせで覚えるのも一つの手です
- 説明や図もしっかりしています
時代順を覚える
まずは時代を順番にノートに書きましょう。歴史が苦手な人は時代の順番を覚えていないことが多いです。
「奈良時代の次は何時代?」と聞かれた時にすぐ答えられますか?教科書や資料集の時代区分を写すだけでいいですので、時代順をしっかりと覚えるようにしましょう。
旧石器・縄文・弥生時代はセットでまとめる
旧石器時代と縄文時代と弥生時代はセットでまとめると効果的です。具体的には表を作ると良いでしょう。
| 旧石器 | 縄文 | 弥生 | |
| 遺跡 | 岩宿遺跡(群馬) | 三内丸山遺跡(青森) | 吉野ヶ里遺跡(佐賀)
登呂遺跡(静岡) |
| 道具 | 打製石器 | 磨製石器
土偶 |
青銅器
石包丁・田げた |
| 建物 | 洞窟 | 竪穴住居 | 竪穴住居
高床倉庫 |
簡単に表にしてみました。(自分でまとめる時はもう少し詳しくまとめても良いかもしれません。)
関連する事柄をセットにして覚えることにより、多くの事柄を覚えることが出来ます。旧石器時代・縄文時代・弥生時代はセットで覚えることで定期テストや公立高校の入試で得点が取りやすくなります。
人物で覚える
弥生時代以降は中心人物で覚えると歴史の流れを掴みやすくなります。
例えば、聖徳太子と関連させて覚える事柄
- 推古天皇の摂政
- 冠位十二階
- 十七条の憲法
- 遣隋使
- 法隆寺
ここで遣隋使に関連させて「小野妹子」を覚えるといったように付随する事柄や人物を覚えるようにすると暗記がしやすくなります。
その時代の有名人物をピックアップすることから始めてみましょう。
文化は別にまとめる
各時代毎に文化があります。文化は文化でまとめると見やすいノートになります。その時代の文化の特徴、書物、絵画、彫刻、建造物などでまとめて覚えることが効果的です。
また、絵画や彫刻、建造物は写真を見ておくことも大切です。
問題を解く
まとめノートの作成が終わったら、問題を解いていくようにしましょう。覚えたことをアウトプット出来るかの確認です。
定期テストや入試ではこのアウトプットが出来ないと得点になりません。問題によっては聞かれ方が違ったりもしますが、覚えた知識を総動員して答えにたどり着くことが出来るか確認をしましょう。
[amazonjs asin=”4010214902″ locale=”JP” title=”高校入試 入試問題で覚える 一問一答 社会”]
- 一問一答式で用語の確認をする
- 過去問を参考に作成されています
[amazonjs asin=”4578231631″ locale=”JP” title=”最高水準問題集 歴史 (中学最高水準問題集)”]
- 定期テスト対策から入試レベルまで
- 解説を読むことが大切です
まとめノートの再活用
出来なかった問題や知らなかった知識が出て来た時は、まとめノートに追加すると効果的です。
したがって、いつも手元にまとめノートを準備しておくようにしましょう。また、最初にまとめる際に空欄を多めに残しておくと追加をしやすくなります。
問題を解く度に新しいことを追加していくことで、自分専用のまとめノートが充実したものになっていきます。
公立高校の入試が終わるまで、まとめノートのレベルアップを図っていきましょう。
映像授業の活用
自分で勉強していると不安になることもあると思います。
やっていることが定期テストや公立高校の入試に役立つのか分からなくなるときもあるかと思います。しかし、塾の授業を受講する予定がない人は映像授業を活用してみるのも一つの手です。
映像授業ということですと「スタディサプリ」が内容と金銭的に良いのではないでしょうか。中学生の歴史の授業は39講座(2017年8月現在)あります。お試し期間もあるので、自分が勉強していることと何か違う点があるかを確認してみてはどうでしょう。
![]()
公立高校へ向けた歴史の勉強のまとめ
まずは歴史に対する苦手意識をなくすことが大切です。苦手意識を持ったまま勉強しても効果はありません。そのため、歴史に興味を持つことから始めるようにしましょう。
興味を持つことが出来たら、ノートまとめをするようにしましょう。いきなり問題を解いても知識がなければ正解にたどり着くことは出来ません。ノートまとめをしながら知識を蓄えるようにしていきましょう。
ノートまとめが完成したら、いよいよ問題に取り掛かります。解けなかった問題については、まとめノートに追加をしていくようにします。この作業により、まとめノートのレベルが上がっていきます。
自分で勉強していることで、抜けていることがないかの確認のために映像授業などのコンテンツを使うことも効果的です。金額的に安いものもありますので、上手く利用すると良いでしょう。
中学社会の歴史分野について見てきました。歴史嫌いのお子様が少しでも歴史に興味を持ち、点数が取れるようになってくれたら幸いです。