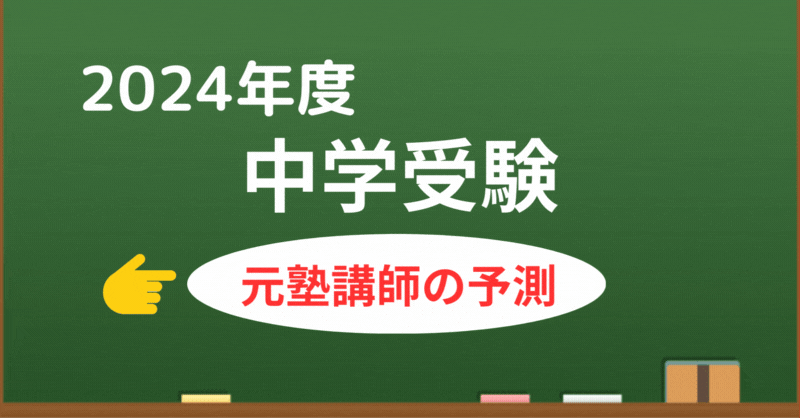小学6年生が受験をする2024年中学入試の予測を元塾講師がしてみました。
あくまでも個人的な予測なので、当たるかどうかは分かりません。
新型コロナウイルスの影響やロシアのウクライナ侵攻ついても考えてみました。
最後に2024年中学入試用の「学校案内」について、リンクを貼っておきました。(2024年度のものが発売されたら張り替えます)併願校選びの参考に1冊あると便利だと思います。
それでは2024年度の中学入試の予測を一緒に見ていきましょう。
2024年度の中学入試の受験者数
2024年の小学6年生の人数は、2023年と大きく変わらないと思います。
小学生の人数は文部科学省が発表している、「学校基本調査」を参考にしています。
ただ、首都圏の小学生の全てが中学受験をするというわけでもありません。
しかし、近年の中学入試の様子を見ていると、増減の幅は僅かではないかと考えています。
参考に2019年度~2023年度の首都圏の中学入試の状況を確認してみたいと思います。
2023年度の首都圏の中学入試の状況は、小学校卒業生数は約29万5000人で、中学受験者数は約6万6500人となっています。
受験率で見ると約23%となっています。
2022年度の首都圏の中学入試の状況は、小学校卒業生数は約29万5000人で、中学受験者数は約6万2400人となっています。
受験率で見ると約21%となっています。
2021年度の首都圏の中学入試の状況は、小学校卒業生数は約29万4000人で、中学受験者数は約6万1700人となっています。
受験率で見ると約21%となっています。
2020年度の首都圏の中学入試の状況は、小学校卒業生数は約34万1000人で、中学受験者数は約6万3000人となっています。
受験率で見ると約18%となっています。
2019年度の首都圏の小学校卒業生数は約29万4000人でした。
そのうち、中学受験者数は約5万500人です。
受験率で見ると約17%となります。
| 入試年 | 卒業生数 | 受験者数 | 受験率 |
| 2023年 | 29万5000人 | 6万6500人 | 約23% |
| 2022年 | 29万5000人 | 6万2400人 | 約21% |
| 2021年 | 29万4000人 | 6万1700人 | 約21% |
| 2020年 | 34万1000人 | 6万3000人 | 約18% |
| 2019年 | 29万4000人 | 5万500人 | 約17% |
徐々に受験率が高くなっています。
景気動向と中学受験
アベノミクスによって、日本経済も回復傾向にありました。
しかし、2018年後半の米中貿易摩擦から新型コロナウイルス、ロシアのウクライナ侵攻など世界経済に停滞の兆しがあらわれています。
- 米中貿易摩擦
- 新型コロナウイルス
- ロシアのウクライナ侵攻
中学受験者数は、リーマンショックの時に大きく減っていますので、景気が悪くなると受験者数は減少すると思います。
しかし、2024年度中学入試は、当時の小学5年生の入試なので、今の時期まで中学受験の勉強を続けてきた人たちは、このまま受験をするのではないでしょうか。
そうすると、2024年度中学入試の受験者数が大きく減少することはないと予測します。
今後、更に景気が悪くなると中学受験者数が減る可能性もあるのではと思っています。
私立中学校の難易度
受験生の保護者の方が一番気にするのは、お子様の志望校の難易度の変化ではないでしょうか。
多くの私立中学校があるので、学校により難易度が大きく違ってきます。
最難関の進学校、いわゆる御三家とよばれる「開成・麻布・武蔵」「桜蔭・女子学院・雙葉」に関しては、難易度が大きく変わることはないと思います。
今年のデータを元に、いろいろなパターンを検討しておく必要があります。
上記の御三家を志望する生徒は、小学4〜5年生の段階で受験校をある程度決めていることが多いため、人気は変わらないのではないでしょうか。
もちろん小学6年生になってから志望をする生徒もいますが、逆に小学4年生の頃から志望校を決めて勉強を始めている生徒も多くいます。
したがって、最難関の進学校に関しては、難易度で大きな変化はないと予測します。
次に、大学付属の私立中学校に関して考えてみると、「2020年度の大学入試改革」「私立大学の定員厳格化」によって現在も人気が続いています。
では、2024年はといいますと、個人的には大学付属校の人気はまだ続くと思います。
人気が続くだけでなく、人気が更に高まるのではないかと考えています。
大学入試の結果が分かり、どういった対策をすればいいのか、難易度はどう変わったのか、などがはっきり分かるまでは、大学付属校の人気が続くと予測します。
最難関の進学校は2024年度以降も人気が続き、大学付属校は景気動向と大学入試改革の結果によっては人気が変わって来るのではないかと思います。
また、併願校に関しては、以前に比べ受験校数が増えてきています。
どうしても私学に進学させたいというご家庭が増えてきているのではないでしょうか。
2023年度 御三家の状況
開成中
受験者数:1193人(前年比143人増) 2.9倍
麻布中
出願者数:918人(前年比16人減)
武蔵中
受験者数:579人(前年比47人減) 3.1倍
桜陰中
受験者数:607人(前年比70人増) 2.1倍
女子学院中
出願者数:700人(前年比69人減)
雙葉中
出願者数:401人(前年比20人増)
その他の難関校
筑波大学附属駒場中
受験者数:521人(前年比42人増) 4.1倍
海城中
受験者数:545人(前年比56人増) 3.4倍
駒場東邦中
出願者数:611人(前年比46人増)
浅野中
出願者数:1734人(前年比3人増)
洗足学園中
受験者数:265人(前年比52人減) 3.2倍
鷗友学園中
受験者数:551人(前年比22人減) 2.8倍
豊島岡中
受験者数:964人(前年比35人減) 2.4倍
2023年度入試の反動
上の「私立中学校の難易度」と関係しますが、2023年度中学入試の結果が出て、その結果を見て志望校を変更してくる家庭が多くあると思います。
一般的に、難易度が上がりすぎると敬遠をする家庭が出てくるので、偏差値は若干下がってきます。
逆に、難易度が下がりすぎると狙ってくる家庭が出てくるので、偏差値は若干上がっていきます。
ただ、偏差値が上昇を続ける学校も中にはあるので、11月と12月の模試の結果を見て判断する必要があります。
進学校の場合、2023年度の卒業生の進学実績が、2024年度中学入試の難易度に影響を及ぼします。
2023年度の中学入試の情報だけでなく、大学進学実績にも目を向けることが重要です。
毎年週刊誌に掲載される「東大合格者数」「早慶大学合格者数」を見ることによって、中学入試で人気になりそうな学校を予測することが出来ると思います。
新型コロナウイルスの影響
2020年4月7日夜に緊急事態宣言が出されました。
また、2021年1月に2回目の緊急事態宣言が出されました。
しかし、最近はコロナのニュースも減ってきています。
また、5月には5類への引き下げが決まっていることも考えると、以前のように中学入試に大きな影響を及ぼすことはないでしょう。
インフルエンザと同じように入試直前にかからないよう注意だけはしておく必要があります。
以前は塾の授業が休校となったりWeb授業になったり、対面式とWeb授業を併用したりなど、様々な対応をしていました。
しかし、最近はまた毎週決まった時間に塾に行き、宿題を提出し、授業を受けていた生活に戻りだしているのではないでしょうか。
Web授業の場合、動画を見るだけになってしまったり、双方向の授業であっても教室の雰囲気ではなくなっていました。
そのため、受験に向けてモチベーションを高めるのが難しかったと思います。
それも塾に行くことができるようになって変わってきました。
今後感染が広がった場合は、中学校も入試に向け何か対応をするとかもしれませんが、現時点ではわかりませんので実力を高めることに専念していきましょう。
新型コロナウイルスは終わることはないかもしれませんが、自分でしっかり計画的に勉強を進めていったお子様が合格を勝ち取れると思います。
通常の生活に戻る流れが続いており、だんだんと元の受験状況に近づいてきています。
夏までの間に、小学6年生の新出単元をしっかりと学習し、夏以降の過去問演習に備える必要があります。
くれぐれも健康管理に気をつけて欲しいと思います。
合格最低点を意識する
過去問に取りかかるようになったら、偏差値よりも過去問の点数に目を向けるようにしましょう。
多くの学校で合格最低点を発表しているので、自分の受験する科目数(2科目・4科目)で確認をするようにしてください。
合格最低点は学校により違いがありますが、おおよそ6割となっています。(中には7割以上の学校もあります)
また、年度によっても合格最低点は違っていますので、解いた年度のものをしっかり確認することが大切です。
合格最低点まであと何点足りないのかを確認し、どの科目のどの単元で点数を取ることが出来るか分析し、次に過去問をやる際に点数が取れるようにしましょう。
記述の採点や漢字間違いの採点など、どうしたら良いか分からないものはお通いの塾の講師に相談することをおすすめします。
また、中学入試の採点基準を下記記事にまとめています。
関連記事>>科目別に中学入試の採点基準を確認して子供に伝えましょう
まとめ
現在の小学6年生が受験をする、2024年度中学入試について書いてきました。
あくまでも、元塾講師が予測する2024年度中学入試についてなので、予測が大きくハズレることがあるかもしれません。
最終的には、11月・12月の模試の結果を見て、その結果をもとに家族で話し合いをして、志望校の最終決定をする必要があります。
2023年度中学入試の新しい情報が出てきましたら、加筆修正をしていきたいと思います。
関連記事>>【中学受験】2024年度用の学校案内(ガイドブック)4冊の紹介
2024年度中学入試用の学校案内が発売されましたら更新をしたいと思います。
併願校を選ぶ参考に1冊準備しておくことをおすすめいたします。
その他に、こちらもおすすめの1冊となります。
[amazonjs asin=”4022793074″ locale=”JP” title=”カンペキ中学受験 2024 (AERAムック)”]