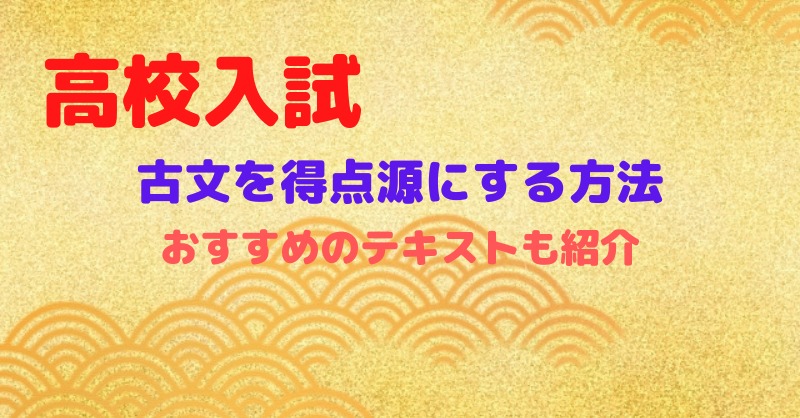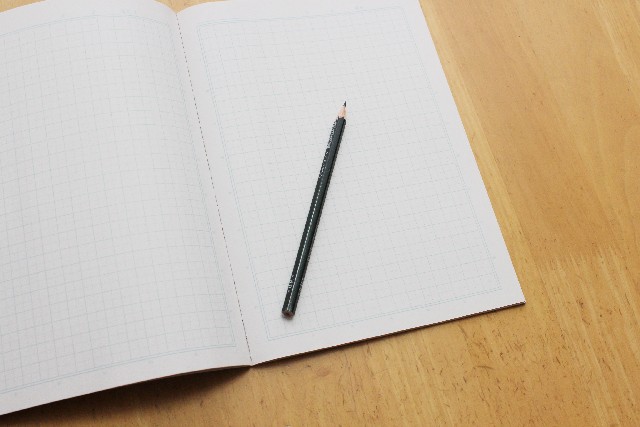高校入試ではかなりの確率で古文が出題されます。
古文と聞くだけで苦手意識を持ってしまう人が多いですが、実は得点源にしやすい分野です。
大学入試の古文を短期間でマスターするのは難しいですが、高校入試であれば比較的短い期間(およそ2ヶ月)で得点源に変えることが出来ます。
今回は古文を得点源にするための勉強方法について見ていきましょう。
中学3年生になってからでも遅くはありませんが、早めに得点源にすることをおすすめします。
中学生が古文を得点源にする方法
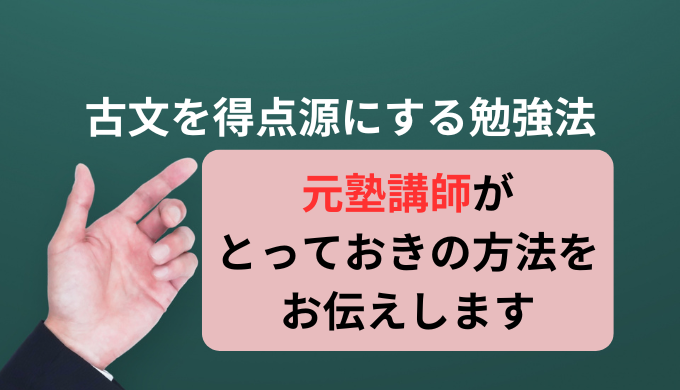
- 中学生が習う古文
- 古文の勉強方法
- 古文の学習の基礎
中学生が習う古文
古文の学習は中学校に入ってから始まります。(小学校によっては暗唱をしていることがあります)
古文は最初の段階で嫌いになってしまうお子様も多いですが、実は得点源にしやすい分野です。
最初に嫌いになってしまう理由としては、「読みにくいし、内容が面白くない」といったことが挙げられます。
もちろん面白い方がいいですが、面白くなくても「古文は得点源になる」と割り切って勉強をするようにしましょう。
中学1年生時に習う古文は、現代語訳がついていることが殆どです。
それが中学2年生になると、現代語訳がつかなくなりどんな内容か分からなくなっていきます。
中学2年生の時点で古文嫌いのお子様が大量発生します。
ただ、中学生が習う古文には、「注書き」が多く出ているので根気強く見ていくと内容が把握できるようになります。
そして、古文の内容把握ができるようになると問題が解けるようになります。
問題が解けて点数が取れるようになると自信がつき、更に勉強するという好循環が生まれます。
古文の勉強方法
中学生の古文は「内容把握」が最も重要となってきます。
内容が分かると殆どの問題が簡単に解けるようになります。
逆に内容が分からないと、勘で解くことになり間違いが多くなってしまいます。
現代語訳を出来るようにする
そこで内容を把握するための練習が必要になります。
練習方法は、「古文の現代語訳をノートに書く!」これが一番効果的です。
ノートに現代語訳ができたら解答解説と見比べてみましょう。
その際、細かい違いは気にせずストーリーが合っているかを重視します。
高校入試の古文はストーリーが合っていれば、大抵の問題は解くことができます。
この練習を毎日1~2題行っていると、およそ2ヶ月後には読んだだけで古文のストーリーが分かるようになります。
入試本番では現代語訳を書くスペースや時間がないので、読んで意味が分かることが大切です。
また、あまり期待してはいけませんが、同じ古文が入試に出題される可能性も高くなります。(中学生が読むことができる古文は多くないので出題される可能性はあります)
古文の学習の基礎
歴史的かなづかいのきまりや古典常識を押さえておくことも非常に重要になってきます。
もう一度基本に戻って確認をしておくようにしましょう。
歴史的かなづかい
現代では用いないかなを用いるもの
ゐ→い ゑ→え
現代とは異なる字を用いるもの
を→お ぢ→じ づ→ず
現代の発音とは一致しない字を用いるもの
は行→わ行 む→ん など
私立高校の入試問題でも現代仮名遣いに直させる問題はよく出題されています。
決まりを覚えておくと確実に得点になるのでおろそかにしないでください。
古典常識
月の異名
睦月(1月) 如月(2月) 弥生(3月)
卯月(4月) 皐月(5月) 水無月(6月)
文月(7月) 葉月(8月) 長月(9月)
神無月(10月) 霜月(11月) 師走(12月)
時刻の表し方
子の刻(午前0時) 丑の刻(午前2時) 寅の刻(午前4時)
卯の刻(午前6時) 辰の刻(午前8時) 巳の刻(午前10時)
午の刻(午後0時) 未の刻(午後2時) 申の刻(午後4時)
酉の刻(午後6時) 戌の刻(午後8時) 亥の刻(午後10時)
基礎の復習をすることで、今まで以上に古文の内容把握が出来るようになります。
『古文完全攻略63選 【入試頻出問題厳選】 (高校入試特訓シリーズ)』はこういった古典知識も網羅されています。
隅から隅まで1冊を徹底してやって欲しいと思います。
古文を得点源にすることのメリット
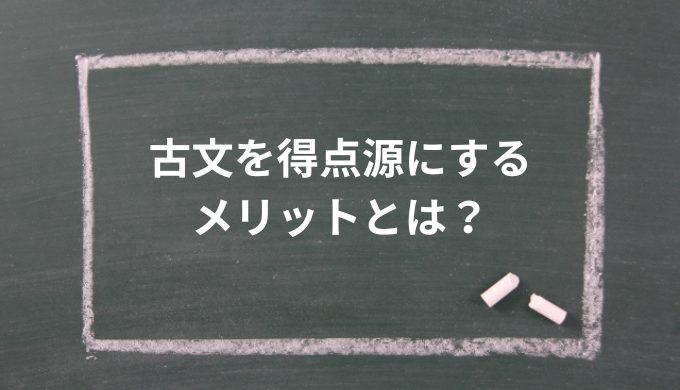
古文を得点源にすることができたら、15~30点くらいは安定的に取れるようになります。
テストでは最後の方に出題されることが多いですが、最初に解いてしまうと気持ち的にも楽になります。
また、時間配分を考えた上でも最初に解くことをおすすめします。
中学3年生からでも十分得点源にすることができるので、毎日1~2題の現代語訳を作る練習をしてみて下さい。
古文ができるようになると、国語で確実な得点源ができ、時間的余裕を持つことができるといったメリットを手に入れることができます。
その際、解答解説に現代語訳がついている問題集を使うことが重要です。
- 古文の勉強におすすめのテキスト
- 古文完全攻略63選の使い方
- 実際に問題を解いてみる
- 塾用の教材よりもおすすめ
- 高校受験に向けて古文を得点源にする方法の総括
古文の勉強におすすめのテキスト
- 多くの古文に触れることで、入試で同じ文章が出題される可能性が高くなります
- 解説が詳しいので1人で勉強出来ます
- 1冊終わらせると、相当力がつきます
「古文完全攻略63選 【入試頻出問題厳選】 (高校入試特訓シリーズ)」の具体的な使い方を見ていきましょう。
古文完全攻略63選の使い方
『古文完全攻略63選 【入試頻出問題厳選】 (高校入試特訓シリーズ)』では第一章と第三章で現代語訳の練習をすることができます。
第一章には古文が20題掲載されており、左側のページに詳しい現代語訳がついているので、まずは現代語訳を隠してノートに自分で訳を作ってみるようにしましょう。
また、現代語訳の他に重要な文法や古語が掲載されているので、訳を見ながら確認をすると効果的です。
第三章には古文が21題掲載されています。
第一章と同じように左側のページに現代語訳がついているので、まずは隠してノートに自分で訳を作るようにしましょう。
また、第三章には例題があるので、訳が出来てから解くようにします。
模範解答と同じような訳が作れていると問題は簡単に解けると思います。
第一章と第三章で41題ありますので、毎日1題ずつ現代語訳を作ったとしても2ヶ月で終わらせることが出来ます。
受験生であれば9月からは現代語訳作成を始め、まずは古文を苦手分野でなくすようにしましょう。
実際に問題を解いてみる
現代語訳が作れるようになってきたら、実際に問題を解いてみるようにしましょう。
その際もまずは現代語訳を作るようにします。
志望校の過去問を時間を決めて解く時以外は、現代語訳を作るようにすると力がつきます。
『古文完全攻略63選 【入試頻出問題厳選】 (高校入試特訓シリーズ)』の第二章には古文が22題掲載されています。
この章は実践問題となっているので、左側のページに現代語訳がついていません。
現代語訳は解答・解説のページに掲載されているので、答え合わせをする前に自分で作った訳が合っているか確認をするようにしましょう。
問題の答え合わせをする際に注意することとして、現代語訳が合っていないのに問題が合っていたという場合は安心してはいけません。
まぐれ当たりということもありますので、しっかりと訳を確認するようにして下さい。
最終的には現代語訳と問題の両方が合うようになることを目指して下さい。
ここまで来れば古文が得意分野に変わっています。
塾用の教材よりもおすすめ
塾で使う教材会社のテキストにも古文の単元はあります。
しかし、1つの単元に掲載されている古文の数はそれほど多くはありません。
また、授業内で解く場合には現代語訳を作る時間がなかったりもします。
そのため、市販の古文専門の教材を準備して自分で対策をすると効果的です。
出来るだけ現代語訳がしっかりとしている教材を使うようにしましょう。
- 入試頻出の古文を集めています
- 現代語訳がしっかりとしています
- 古文の掲載数が多いです
一度読んだことがある古文が高校入試の問題で出題されると他の受験生に比べ非常に有利になります。
多くの古文を読んでおくと同じ問題が出題される可能性が高くなります。
事前に多くの古文を読んでおくためにもおすすめです。
高校受験に向けて古文を得点源にする方法の総括
古文と聞くと難しいイメージがありますが、高校入試レベルであれば得点源にすることが可能です。
学校の定期テストとは勉強の仕方が異なる部分もありますが、常に現代語訳を出来るようにしておくと問題が解けるようになります。
古文に慣れることが大切ですので、1日1〜2題の現代語訳をノートに作るようにしていきましょう。
今まで指導してきた多くの生徒が、上記の方法で古文を得点源にすることが出来ました。
中学3年生はもちろんですが、早い段階で古文を得点源にすることが出来ると国語に対しての苦手意識をなくすことが出来ます。
ぜひ中学1~2年生の方も、現代語訳を作る練習をして古文を得点源にして欲しいと思います。